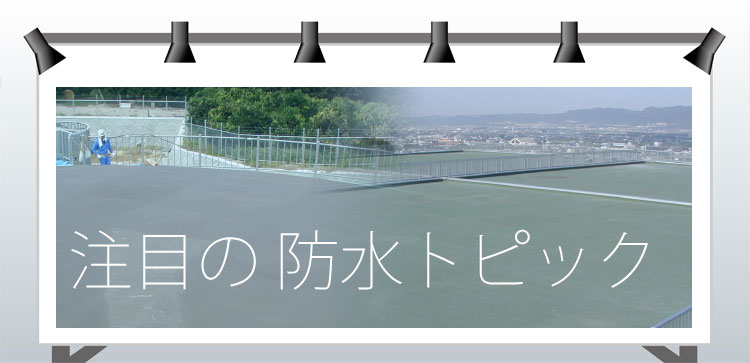ウレタン防水の特長と、広がる防水工法の選択肢
長年多くの現場で採用されてきたウレタン防水材。その特長と実績は今も変わりませんが、建物の用途や施工環境によっては、別の材料・工法が選ばれることもあります。ウレタン防水と他工法の特長を比較し、最適な工法選びのポイントを事例とともにご紹介します。
ウレタン防水の特長
ウレタン樹脂系塗膜防水は、液体状のウレタン樹脂を塗り重ねてシームレスな防水層を形成する工法です。屋上やベランダ、バルコニーなどの防水対策として、新築・改修の両方で広く採用されています。
複雑な形状や立ち上がり部、配管まわりなど細かい箇所にも施工しやすく、継ぎ目のない仕上がりは防水性能の安定にもつながります。施工直後は光沢感があり、美観性にも優れています。
材料の伸び性能も高く、建物の動きに追随しやすいため、モルタル下地や軽量コンクリートなど微細な動きが出やすい部位にも適しています。

乾燥時間は比較的早く、条件が良ければ翌日には次工程に移れるケースも多く見られます。
一方で現状の主流は溶剤系であり、施工時には特有の臭気が発生します。
また湿潤面での施工はできないため、天候や下地乾燥の条件によっては工程を延期せざるを得ない場合もあります。
臭気の少ない水性ウレタンも市場に登場していますが、価格も通常タイプより若干高めであることから、現時点では普及は限定的です。
他工法が選ばれる場面と背景
臭気への配慮が求められる現場
改修工事では、対象の建物・施設を利用する中で施工を行うことがほとんどです。
特に病院や高齢者施設、学校、商業施設、集合住宅などでは、施工中も利用者が日常生活を送っています。
溶剤系材料を使用すると、その揮発性成分が施工範囲を越えて室内や共用部にまで広がることがあります。
においに敏感な方や呼吸器系に負担を感じる方への影響が懸念され、特に高齢者や小児、持病を持つ患者、免疫力が低下している方にとっては、健康被害につながりかねません。
事例1:高齢者施設屋上改修
関西地方のある高齢者施設では、築20年を超えた屋上防水改修を計画していました。
当初はウレタン防水を採用予定でしたが、施設内の食堂や居室にまで臭気が届き、利用者の食欲低下や頭痛が懸念されるとの声がありました。
そこで、臭気の少ないポリマーセメント系塗膜防水に変更。
工事中も食事や日課を中断することなく進められ、「においが気にならないので安心できる」との評価を得られました。
事例2:総合病院外来棟屋上改修

都市部の総合病院では、外来患者や付き添い家族の出入りが多く、施工期間中も診療を休止できません。
溶剤臭が外来ロビーに入り込めば、苦情や来院者減少に直結する恐れがあり、入院患者や職員への影響も懸念されました。
そこで、有機溶剤を含まない水性系材料を採用し、換気装置を併用することなく、きつい臭気をほとんど感じない環境を実現しました。
湿潤面での施工が必要な現場
ウレタン防水材は湿潤面での施工ができないため、下地が完全に乾燥している必要があります。
そのため、雨上がりや梅雨時期、風通しの悪い環境では工程が延びることもあります。
一方、ポリマーセメント系塗膜防水は水性であるため、湿潤面でも施工可能です。
ここでいう湿潤面とは、手で触れると湿っていると感じる程度の状態であり、水たまりができている状況は含みません。
事例3:学校屋上改修(梅雨時期)
梅雨が重なる夏休みの合間を狙って行う地方都市の小学校屋上改修では、連日の降雨で下地が乾燥せず、ウレタン防水では日程が組みにくい状況でした。
湿潤面施工が可能なポリマーセメント系を採用し、梅雨明けを待たずに工事を完了。
夏休み期間中の体育館や教室の利用に支障を出さず、高評価を得ました。
環境配慮・作業環境改善を重視する現場
近年、防水材の分野でも「VOC(揮発性有機化合物)」の低減が求められています。
VOCとは、大気中に揮発しやすい有機化合物の総称で、シックハウス症候群や大気汚染の原因の一つとされ、健康や環境への影響が懸念されています。
ウレタン防水では、低VOC型製品も登場し、従来より排出量を抑えることが可能になっています。
しかし、主流である溶剤系の場合、施工時には一定量のVOCが発生します。
一方、ポリマーセメント系塗膜防水材は水性のため溶剤を使用せず、施工時のVOC発生をほぼゼロに抑えられます。
そのため、施工環境の快適性や周辺環境への配慮という面で優位性があり、特に人の出入りが多い医療施設・高齢者施設・学校・商業施設などで採用が増えています。
また、ポリマーセメント系は【特化則(特定化学物質障害予防規則)】の配慮も不要です。
ウレタン防水材の主剤や硬化剤には、TDI(トルエンジイソシアネート)やMOCA(ジアミン系硬化剤)など、特定化学物質に該当する成分が含まれる場合があり、場合によっては作業者への安全管理が必要となります。
事例4:公共施設の外壁防水改修
役所庁舎や公民館等、公共施設の外壁防水改修では、施設利用中も工事を実施。
来館者の通行ルートや施設周への臭気・飛散が懸念されました。
臭気の少ない工法(本例では水性のスカイコートW)を採用し、施工範囲を細かく区切って段階的に進めることで、利用者への影響を最小限に抑えました。
結果として、工事中も売上や来館者数に影響は見られませんでした。
工法比較表(特性一覧)
| 項目 | ウレタン防水(溶剤系) | ポリマーセメント系塗膜防水 |
| 臭気 | △(施工時に強い) | ◎(溶剤臭は無し) |
| 湿潤面での施工 | × | ◎ |
| 仕上がりの光沢感 | ◎ | ○(ややつや消し調) |
| 材料の伸び性能 | ◎ | ○ |
| 普及度・入手性 | ◎ | ○ |
| 施工実績の多さ | ◎ | ○ |
※◎=優れる、○=良好、△=制約あり、×=不可
適材適所での防水計画
ウレタン防水には、仕上がりの美しさ、柔軟性、豊富な実績という揺るぎない魅力があります。
しかし、建物の用途や施工環境、作業時期によっては、臭気対策や湿潤面施工などの面で他工法がより適している場合もあります。
重要なのは、「どの工法が一番優れているか」ではなく、「その現場にとって何が最も安心で、長く持つか」を見極めることです。
防水層は普段は目に見えませんが、万が一の不具合は建物全体の価値や使用環境に直結します。
だからこそ、施工前の計画段階から適材適所の判断を行い、5年ごとのトップコート塗り替えや、10年後の改修工法検討といった、将来のメンテナンスサイクルを見据えた選定が欠かせません。
大日化成では、ポリマーセメント系塗膜防水をはじめとする多様な工法の経験を活かし、お客様の建物に最も適した防水計画をご提案します。
単なる工法の紹介にとどまらず、工事後の維持管理や将来の改修計画まで視野に入れたご提案を行うことで、「今」だけでなく「これからの安心」もお届けします。

BIG SUN(屋外屋内用)商品ページ
https://www.dainichikasei.co.jp/product/bigsun1/