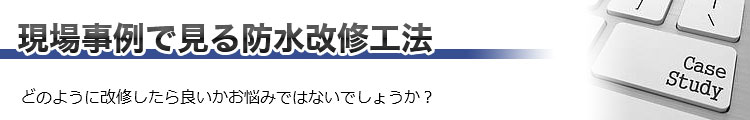新築から数十年。日本全国で防水を改修しなければならない時期に来ています!
昭和の負の遺産ともいえる、高度成長期に建築された建造物から、比較的新しい平成初期の建造物。バブルの頃に建ち並んだ建造物。これらの防水は悲鳴を上げています。
防水材メーカーとしては概ね10年を目処に防水の改修をお願いしておりますが、実際には遅々として進んでいないのが実状ではないでしょうか。しかしながら漏水がおこれば改修せざるを得ません。また計画的に防水改修工事を計画しているところも多数ございます。
しかし新築とは違い、いったんなにがしかの防水工法で施工されたものを改修するのですから、新築時のような自由度は無いと言っても過言ではありません。例えば、防水改修工事の大半は、『入居者がいる』ことが大半です。そうなると、工事が慎重になります。第一に居住者への安全配慮。そして工期、騒音、振動、臭気など様々な条件をクリアしなければなりません。かつ、コストパフォーマンスも検討しなければならないでしょう。
そういった諸条件のもと、防水改修工法をご提案するのにお悩みではないでしょうか?
こちらでは、そういった諸条件ごとに、どのような課程で防水改修工法が選択され施工されたかをケーススタディとしてご紹介いたします。

Vol.67 完全水性で匂いの問題がない防水材であることが重要なケース
Vol.66 現場に有機溶剤を持ち込む必要がない安全なエポキシライニング材であることが重要なケース
Vol.65 意匠性を担保する観点から、透明度が高い塗膜である防水材である事が重要なケース
Vol.64 改修工事のため臭気のあるものはNGかつタイルの意匠性を担保することが重要なケース
Vol.63 軽量かつ遮熱効果があり、手塗り施工出来る防水材であることが重要なケース
Vol.62 病院の改修という特殊性から極力臭気の少ないことが重要なケース
Vol.61 既存防水材との相性が良く、役物が多いことから施工性の良いことが重要なケース
Vol.60 有機溶剤を含まず安全な作業が行なえる事が重要なケース
Vol.59 水質試験に合格しており、耐オゾン性能を有する事が重要なケース
Vol.58 溶剤プライマーを施工しても強度の低下を起こさない素地調整材であることが重要なケース
Vol.57 受水槽であることからも臭気が少なく安全で水質試験に合格していることが重要なケース
Vol.56 水質検査に適合しかつ臭気が無く安全に施工出来ることが重要なケース
Vol.55 通院、入院患者に配慮して振動・騒音・臭気が極力ない事が重要なケース
Vol.54 部分改修が目立たすことなく確実に防水ができる事が重要なケース
Vol.53 下地に水分が含まれている為通気緩衝工法で騒音や振動もなく安全に施工出来ることが重要なケース
Vol.52 手を尽くしても止まらない水漏れを防ぎ、下地(タイル)の意匠性を損なわないことが重要なケース
Vol.51 将来的に目地にひび割れがしても防水性能を担保出来て、意匠性も損なわないことが重要なケース
Vol.50 使用材料が全て水系であり振動・騒音の問題も無い通気緩衝工法であることが重要なケース >>>
Vol.49 オール水性で臭いのトラブルが無く湿潤下地でも施工可能な事が重要なケース >>>
Vol.48 既存タイルの意匠を活かせる透明塗膜である事が重要なケース >>>
Vol.47 過去実績があり臭気も無いポリマーセメント系塗膜防水材が必須である事が重要なケース >>>
Vol.46 臭気の問題が無く施工業者の方にも扱いやすい事が重要なケース >>>
Vol.45 有機溶剤等の危険物を現場に持ち込まず、極力臭いの少ない防水材である事が重要なケース >>>
Vol.44 有機溶剤等の危険物を現場に持ち込まない必要がある事が重要なケース >>>
Vol.43 防水は元より外観を損なわない仕上がり感が重視されたケース >>>
Vol.42 透明度の高さを重視し既存タイルの意匠性を損なわないことが必須だったケース >>>
Vol.41 下地に密着し極力臭気のしない壁面防水材であることが必須であったケース >>>
Vol.40 タイルの意匠性はそのままに漏水を完全に止めることが必須であったケース >>>
Vol.39 壁面での防水効果を発揮しかつ意匠性を変えない事が必要だったケース >>>
Vol.38 臭気問題でNGにならず完了検査を一発で通る必要があるケース >>>
Vol.37 公営住宅改修工事において危険な要素を取り除く必要があったケース >>>
Vol.36 外壁タイルの目地シール打ち替えに変わる工法が必要なケース >>>
Vol.35 臭気の問題が無く受水槽という特殊な環境下でも安心して使用して頂ける事が必要なケース >>>
Vol.34 溶剤等の危険物を一切現場に持ち込まない必要があるケース >>>
Vol.33 既存タイルの意匠性をかえずにタイルを活かしたいことが必要なケース >>>
Vol.32 既存の通気緩衝工法ビッグサンRX工法塗膜を侵蝕しないトップコートが必要なケース >>>
Vol.31 艶ありタイルの意匠性を損なわない防水材が必要なケース >>>
Vol.30 外壁タイルからの漏水を、臭気が無くタイルの意匠性を損なわない防水材が必要なケース >>>
Vol.29 飲料水対応で弾性を有するポリマーセメント系塗膜防水材が必要なケース 詳しくはこちら >>>
Vol.28 全ての材料が1剤型の水系で臭気が無く透明度が高い仕上がりが必要なケース 詳しくはこちら >>>
Vol.27 透明度が高い防水材であり、臭気の少ない材料であることが必要なケース 詳しくはこちら >>>
Vol.26 全てが水系材料で、火災や溶剤による中毒の心配がない事が必要なケース 詳しくはこちら >>>
Vol.25 外壁意匠を担保しつつ臭気の少ない防水材であることが必要なケース 詳しくはこちら >>>
Vol.24 下団D種に適合することが必要であったケース 詳しくはこちら >>>
Vol.23 臭気が無く有機酸に耐えうる防食性能を持つことが必要であったケース 詳しくはこちら >>>
Vol.22 既存外壁の意匠をそのまま活かせる必要であったケース 詳しくはこちら >>>
Vol.21 JWWA K143の品質規格に適合し安全な材料が必要であったケース 詳しくはこちら >>>
Vol.20 塗装ではなく、防水性能のある防水工法が必要であったケース 詳しくはこちら >>>
Vol.19 大面積に対応可能で、下地を選ばず火気厳禁が必要であったケース 詳しくはこちら >>>
Vol.18 壁面に塗膜を形成する防水材が必要であったケース 詳しくはこちら >>>
Vol.17 安全性が高く日本水道協会の規格JWWA K143適合が必須であったケース 詳しくはこちら >>>
Vol.16 密集した民家での防水改修の為に、無臭・静音が必須であったケース 詳しくはこちら >>>
Vol.15 防水・無溶剤・有機酸に耐えられる事が必須であったケース 詳しくはこちら >>>
Vol.14 改修工事も新設と同じく厳しい条件をクリアする必要があるケース 詳しくはこちら >>>
Vol.13 騒音臭気がなく、低気温でも即硬性のある工法が求められたケース 詳しくはこちら >>>
Vol.12 通気緩衝工法で大規模面積対応および臭気の無いものが求められたケース 詳しくはこちら >>>
Vol.11 真夏の炎天下でも諸条件を克服できることが求められたケース 詳しくはこちら >>>
Vol.10 騒音や振動が極力無く、下地を侵食しないことが求められたケース 詳しくはこちら >>>
Vol.09 柱のない屋根の為に大きい揺れに追従できることが求められたケース 詳しくはこちら >>>
Vol.08 臭気や火災発生の危険から安全な防水材料が求められていたケース 詳しくはこちら >>>
Vol.07 臭気も少なく、水質試験に合格していることが必須だったケース 詳しくはこちら >>>
Vol.06 交通規制が必要の為、施工が短時間で終わることが必須だったケース 詳しくはこちら >>>
Vol.05 凹凸があり安全でシームレスな塗膜防水が必須だったケース 詳しくはこちら >>>
Vol.04 臭気が少なく「遮熱が必要」だったケース 詳しくはこちら >>>
Vol.03 FRP防水の上に施工でき通気緩衝であり、騒音に配慮が必要だったケース 詳しくはこちら >>>
Vol.02 JWWA K 143に適合した材料であることだったケース 詳しくはこちら >>>
Vol.01 シート防水などの貼りものが不可だったケース 詳しくはこちら >>>